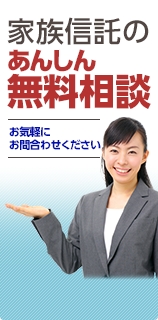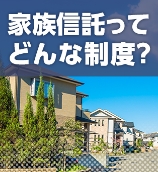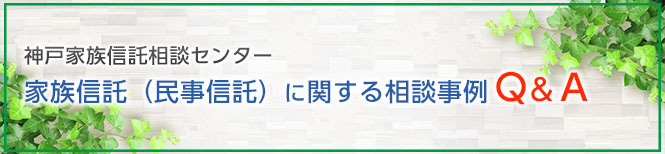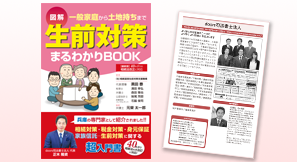2020年12月09日
Q:父は家族信託で叔父の受託者でした。父が亡くなって、私がその地位を引き継ぐべきか司法書士の先生にお伺いします。(明石)
司法書士の先生にお伺いしたいことがあります。私は明石に住む50代の会社員です。私の父は数年前から家族信託を利用し、私の叔父の受託者となって叔父が所有している明石にある駐車場の管理や運営を行っていました。先日父が77歳で亡くなり、相続人は私だけでしたので私が父の遺産を相続することになりました。私が父の財産を相続した場合、父の受託者の地位も私が相続し、私が叔父の駐車場の管理を行わなければならないのでしょうか?私は明石にある会社に勤めるごく普通の会社員ですし、管理職として忙しく働いており、叔父の不動産の管理をする時間的余裕はありません。もし受託者の地位を引き継がなければならないようでしたら生活もガラッと変わってしまうように思います。できれば引き継ぎたくはないのですが、どうしたら良いでしょうか。(明石)
A:家族信託の受託者の地位は原則引き継ぎません。
結論から申しますと、受託者の地位は相続人には相続されません。「受託者」とは「ある人(委託者)から財産を託されて、管理をする人のことで、委託者と契約を交わして財産管理を任される人のことを言います。委託者はほとんどの場合、受託者を決める際「この人に信託財産をお願いしたい」と思って家族信託を結んでいますので、相続の際に受託者の地位が他の相続人に受け継がれてしまうと、委託者が希望した人物ではなくなってしまうため、委託者の意に反してしまいます。
したがってご相談者様はお父様の受託者の地位を引き継ぎ、叔父様の受託者となる必要はありませんが、もし家族信託の契約書に第二受託者をご相談者様とするというような記載があればご相談者様が今後の受託者となり、記載がない場合は、委託者と受益者の合意をもって決めることが可能です。
明石の皆様、家族信託では様々な財産管理を設計する事が可能となります。新しい財産管理である家族信託は、従来の財産管理方法より自由度が高く、ご自身の将来についてよりご希望に近い対策をする事が可能です。明石の皆様のご家庭に合った信託を設定するためにも、家族信託の経験豊富な専門家に相談することをおすすめ致します。明石家族信託相談センターでは、初回無料で明石の皆様のお悩みをお伺いしております。明石にお住まいの皆様、ぜひ一度明石家族信託相談センターの無料相談をご利用ください。明石の地域事情に詳しい専門家が家族信託に関するご相談を親身になってお受けいたします。明石家族信託相談センターのスタッフ一同明石の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2020年11月26日
Q:将来、自宅の売却をしたいと考えているのですが、家族信託の制度を利用して今のうちから何か出来ることはないでしょうか。司法書士の先生にお伺いしたいです。(稲美町)
私は稲美町に暮らす75歳の男性です。5年ほど前に妻は他界し、三人の子供達はそれぞれ結婚をして稲美町とは遠く離れた場所で暮らしています。私が現在一人で暮らしている稲美町の自宅は、築年数が経っており老朽化しているため、子供たちが相続をしたとしても迷惑になるのではないかと考えています。また私自身は老人ホームへの入居を予定していますので、将来的には自宅を売却し、そこで得た資金は老人ホームの施設費に、残りは三人の子供達に分配しようと思っています。しかしながら私はいつ認知症になってもおかしくないですし、その場合の不動産売却の手続きには少々不安があります。家族信託の制度を利用して何か事前に出来る事はありますでしょうか?(稲美町)
A:家族信託で自宅を信託財産に設定しておくことにより、ご相談者様が売却の手続きを行えない状況になったとしても、受託者の権利で手続きが行えます。
神戸家族信託相談センターにご相談いただきありがとうございます。家族信託の活用は財産管理の側面もありますが、今後ご相談者様がより良い人生をおくるうえでも、非常に有効な手段となります。まだまだ世間的な認知度は低いかもしれませんが、遺言や成年後見では解決が難しかった問題も、家族信託の活用次第で解消できることがあるといっても過言ではありません。
今回のケースの場合、ご相談者様が将来介護施設等に入居する際、その資金確保としての不動産売却を行うことが出来るのかをご不安を抱えていらっしゃるという内容ですが、家族信託の制度を利用すると、信託しておいた財産の管理や処分を受託者に託すことが出来るようになるため、万が一ご自身が認知症等になっていたとしてもご自宅売却の手続きを進めることが出来ます。そのためには事前に受託者と家族信託契約を結び、自宅を信託財産に設定する必要があります。財産の管理を任される受託者の決定は非常に重要ですので、誰に依頼するのかよくよくご検討ください。誰でも受託者になることができますので(未成年者、成年被後見人及び被保佐人を除く)、お子様たち、信頼できる知人、一般社団法人などの法人等をご検討されてみてはいかがでしょうか。
今回のご相談者様の信託財産はご自宅で、ご相談者様が委託者かつ受益者となります。受益者とは信託財産から収益を得る人のことで、自宅を売却した後の残金はご相談者様の指定する口座に入ることとなります。
なお家族信託とよく比較されるのが成年後見制度です。成年後見制度により成年後見人となった人は職務として成年被後見人の財産管理と身上監護を行うことになります。成年後見人も財産管理を行うことが出来ますが、自宅を売却するためには家庭裁判所の許可を必要とするため、家族信託契約を事前に結んでいた方がスムーズに手続きが進められるでしょう。ただし施設に入居するための手続きや入院の手続き等は身上監護の範囲となり、受託者では行えませんので、家族信託の契約と併せて任意後見契約(将来的に自分の任意後見人になる人を選び、契約を結ぶ)も一緒にお考えいただくことをお勧めします。
神戸家族信託相談センターでは家族信託に関するご相談事をお受けしております。家族信託は複雑に思われるかもしれませんが、その分自由度が高く、いままでの法律的な手続きでは限界であった希望を叶える可能性があります。家族信託の活用次第で様々な可能性があります。まだまだ家族信託は聞きなれないと感じるかもしれませんが、家族信託の仕組みや活用の仕方などを詳しくお伝えいたしますので、稲美町にお住まいの皆様、ぜひ一度神戸家族信託相談センターの無料相談をご利用ください。
2020年10月23日
Q 家族信託と遺言の違いについて司法書士さんにお伺いしたいです。(播磨)
最近、私の住む播磨でも家族信託という言葉をよく耳にすることが多くなりました。私は現在65歳で特に大きな病気もしていませんが、先の事を考える年齢になってきたこともあり、家族信託の仕組みについてお伺いしたく問合せ致しました。私が健康に暮らしている今のうちに、真剣に今後の子供たちの相続について考えたいと思っています。また、相続対策について調べていくなかで、家族信託と遺言書の違いが良く分からず、結局どちらがいいのか、家族信託の特長や遺言との違いを比較して頂き、司法書士の先生にアドバイスをいただきたく存じます。(播磨)
A 家族信託の一番の特長は、生前からの柔軟な財産管理が可能になることです。
遺言と家族信託の制度の大きな違いは、効力の発生する時期が異なるという点です。
多くの方は「遺言書さえ書いていれば問題ないだろう」と思っているかもしれません。しかしながら、認知症を患ってしまった場合など遺言書では対応が困難な事例も存在します。認知症になってしまうと本人による財産管理は困難になります。
遺言の場合、遺言を書いた本人が亡くなった後からその効果が生じます。一方、家族信託では信託契約を結んだ時に効力が発生するので、本人が生前のうちから効力を発生させることが可能となります。また、この効力は亡くなったあとも維持させることが出来ます。
つまり、あらかじめ家族信託の制度を用いて財産管理を信頼できる家族に託しておけば、介護や通院等にかかる多額の費用が家族の負担とならずに済むという事です。
他にも遺言との大きな違いとして、柔軟な財産管理が可能になるという点があります。遺言では本人から見て直後の行き先のみしか指定できませんが、家族信託では連続した行き先を指定することが出来るようになります。「健康なうちは自分と息子で財産の管理をし、認知症になったら全ての管理を息子に委ね、他界したら妻と息子にそれぞれ財産を相続させる」といった内容を信託契約書にまとめて定めることで財産の有効性が高まります。従来の相続対策では不可能だったことが可能になった、そんな家族信託の需要は今後も増えていくと思われます。
神戸家族信託相談センターでは播磨の家族信託の専門家として、今回のようなご相談も播磨の皆様の親身になってご対応させて頂きます。家族信託制度は非常に難しく、またご自身やご家族にとって一生のことですから戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか。その際には播磨の地域事情に詳しい、家族信託を専門としている当センターの司法書士へご相談される事をお勧めいたします。神戸家族信託相談センターでも数多く播磨の皆様のお手伝いをさせて頂いておりますので、播磨で生前対策についてご相談のある方は当相談センターまでお気軽にお問合せ下さい。播磨の皆さまからのご連絡を所員一同お待ち申し上げております。
18 / 26«...10...1617181920...»
まずはお気軽にお電話ください
0120-079-006
平日 9:00~20:00 [土・日・祝も相談対応]